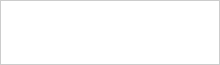私は、日本共産党を代表し、「敬老パス制度の存続と拡充を求める請願」並びに、陳情第1号、第16号、第18号、及び第38号について、採択すべき、との立場で討論をおこないます。
私は、日本共産党を代表し、「敬老パス制度の存続と拡充を求める請願」並びに、陳情第1号、第16号、第18号、及び第38号について、採択すべき、との立場で討論をおこないます。
札幌市は、 2023 年11月に、「敬老健康パス」素案を発表し、高齢者の健康寿命延伸施策として、健康活動にアプリでポイントを付与し、敬老パスへのチャージや、電子マネーで使えるという案を打ち出しました。
これには市民から大きな反発がおこり、それを受け、本市議会でも、敬老パスと健康寿命延伸事業は別々に検討すべきだという議論が行われました。
その後、昨年9月に公表された新たな変更案では、敬老パスと健康アプリ、別々の施策とされたものの、敬老パスを大幅に削減するものでした。
敬老パスは70歳から5歳引き上げるのにひきかえ、健康アプリのポイントを電子マネーに交換できる対象は5歳引き下げて、65歳からです。
しかも上限なく高額なポイント制とした理由は、「当初の敬老健康パスは、敬老パスを全面的に健康ポイント制度に置き換えることを想定し、利用者の平均的な給付水準を考慮して2万円上限のポイントとして提示していた。健康アプリと、敬老パスとの選択制としたので、多くの方に参加していただくためのインセンティブとして、当初の素案と同程度の水準で進めていくもの」と、3月11日の予算特別委員会で答弁がありました。
敬老パスを削減することで利用者が減る想定をし、5年後には検証し見直すとのことですから、当初の、敬老パスを全面的に健康ポイント制に置き換える想定ということは変わらないのでは、敬老パスをなくすのではないか、と市民は懸念しています。
敬老パスの制度は、50年の間、市民に喜ばれてきました。本市の実態調査アンケートでも「敬老パスがあるおかげで楽しみや生きがいを得ることができる」「趣味の種類も増えました。経済効果もあると思います」「出かける機会が増えました」と感謝も多数寄せられています。そして、「70歳が楽しみ」と、自身が敬老パスを使えることを心待ちにし、制度をささえてきたのです。
請願の趣旨説明では、「限度額いっぱいボランティアや通院、買い物に利用している日常であり、敬老パスで大変助かっている」、若い子育て世代の方からは、「敬老パスに反対する若い人ばかりではない。お年寄りを大切にする札幌市でいてほしい」と発言がありました。
そしていまなお、現行制度のまま存続してほしい、また、自己負担額が多少上がっても、年齢は70歳としてほしい、自己負担5割では高い、上限は4万円では少ない、などの多数の声が続いています。
例え、来年度予算が可決されるとしても、それをもって敬老パスの変更案が市民に認められたことになるとはいえず、市民の納得、理解は得られていません。
市民の声を真摯に聞き、財源の問題があるならば、市民に正確な情報を伝え、敬老パスと健康アプリについて市民と相談し、一致できる点を探り、検討すべきです。それが市民との信頼関係の再構築となりえます。
このたびは陳情、請願が次々と出され、また市長あてに提出された署名も5万5千を超えています。市民の声を届ける立場として、請願と陳情を採択すべきであると呼びかけまして、私の討論を終わります。