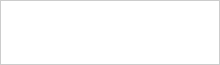私は、日本共産党を代表し、市政の重要課題について、順次質問いたします。
私は、日本共産党を代表し、市政の重要課題について、順次質問いたします。
はじめに、市長の政治姿勢についてです。
質問の第1は、石破政権と新年度予算案についてです。
石破新政権が誕生し最初となる2025年度予算案は、11年連続で軍事費が過去最大を更新し、初の8兆円越えとなる一方で、充実されるべき社会保障分野は自然増分が抑制され、長期化する物価高騰にも有効な手立てが講じられていません。人手不足を解消するためには、その大元にある少子化に歯止めをかける必要がありますが、有効な手立てである大幅賃上げや、地域経済を支えている中小企業への支援には背を向けています。
石破首相は、大軍拡の財源について、4分の3を歳出改革などで賄い、残りの4分の1は税制措置で対応するとしています。
こうした大軍拡予算は、くらし・福祉等の歳出削減、政府債務の増大による増税を招き、市民生活をより困難にし、地域経済の悪化を引き起こすおそれがあり撤回すべきと考えますが、市長は政府予算案をどのように評価されているのか伺います。
質問の第2は、2025年(令和7)度予算案についてです。
本市の2025年度予算案は、一般会計予算が、前年度比249億円増の1兆2,666億円、特別会計・企業会計を含む全会計予算は、前年度比450億円増の1兆9,761億円と、過去最高額を更新しています。
市長は予算提案で「市民生活を支えるために物価高騰や人手不足などの喫緊の課題に取り組むもの」と、説明されました。現在「失われた30年」とも言われる長期にわたる経済停滞の下で、賃金や年金の引上げはまったく追いついておらず、さらに国保料や介護保険料、後期高齢者保険料も上がり続けています。
本市の「消費者物価指数」は2020年を100とし比較をすると2024年は、107.6と政令市中2番目に高い上昇率となっています。
予算編成は、市民の暮らし応援こそ最優先すべきですが、寒さが厳しい中での暖房費の補助や、市民からの要望が多い学校給食費の無償化などの予算は組まれておらず、むしろ市有施設にかかる物価高騰分を、利用者負担の増額で賄うことで、費用削減を図るなど、市民への負担をさらに強いることが行われようとしています。
予算案は、市民の暮らしの困難を打開するという観点が乏しいと言わざるをえません。もっと暮らしを支えるあたたかい施策が求められます。
1点目は、重点支援地方交付金の活用についてです。
国は、予算編成にあたって2024年度補正予算と一体的に、2025年度予算を着実に実行に移し、切れ目のない経済財政運営を推進するとしています。2024年度補正予算で、住民生活に向けて打ち出された施策では、「重点支援地方交付金」による低所得世帯への給付事業がすでに本市においても進められているところです。
重点支援地方交付金は、他に「推奨事業メニュー枠」として、前年度比1千億円増の6千億円が計上されました。
本市は交付金を活用し、学校給食費の保護者負担の据え置きや保育所等の食材費の物価高騰への支援、タクシー事業者へのガソリン代への支援等が補正予算に計上されています。また、市民生活を幅広く支援するためとして、10・11月の水道基本料金、1世帯、約2,900円を免除する事業を進めようとしています。システム改修が必要であるため、免除は8ヶ月ほど先になると聞いています。
重点支援地方交付金の推奨事業メニューには、「消費下支え等を通じた生活者支援」として、灯油等の給付支援のメニューが含まれています。
本市では、市民から毎年「灯油代への補助を求める要望」が上がっており、フルタイムで働く労働者からも「家では、来客がないときはダウンを着込みストーブをつけない」等の実態を聞いています。
数年にわたり続いている灯油代高騰の影響は、家計を直撃するものとなっています。
重点支援地方交付金を活用し、本市の財源も繰り入れて、灯油代への補助事業に取組むべきと考えますが、市長の認識を伺います。
2点目は、子ども医療費助成の所得制限撤廃についてです。
子ども医療費助成は、18歳まで通院・入院費の無償化が拡充されます。
しかし残念なのは「所得制限・初診料をなくし完全無償化にしてほしい」という市民の要望に応えるものになっていないことです。
市長は記者会見で、所得制限の撤廃について問われ「これらは、国や北海道の支援はなく、限りのある自主財源で行っていかなければならず、所得制限撤廃まで踏み切れるだけの財源の余力がなかった」と答えています。
しかし市民からは、2024年本市議会に「医療費助成の所得制限撤廃」を求める陳情が2本提出されています。「所得制限があることで金銭的理由から受診控えが起きることも考えられ、重大な病気の早期発見の機会を奪うものだと考える」、「すべての子どもたちを平等に扱ってほしい」というものです。
そのような実態は、本市が行った「2021年札幌市子どもの生活実態調査」にもあらわれており、上位・中間所得層の中にも「子どもに必要な病院受診をさせなかった経験がある」という回答がありました。
所得制限撤廃に係る費用は毎年約10億4,000万円です。
子ども医療費助成の所得制限撤廃に向けた予算をつけるべきと思いますがいかがか伺います。
また、初診料の負担も撤廃する検討を急ぐべきと思いますがお考えを伺います。
3点目は、敬老優待乗車証交付費の予算についてです
1つ目は、敬老パス制度の効果の認識についてです。
2025年度予算の敬老優待乗車証交付費は、現敬老パスのシステム改修費約9千万円を含め、約68億円です。このうち利用者の自己負担額の見込み額は約12億円であり、これらを差し引くと約56億円が、本市の一般財源からの支出となります。事務費を除く約49億円は、高齢者が敬老パスを利用して出かけることで、地下鉄や市電の乗車料金として、また、経営に困難を抱えているバス事業者へ運賃として支払われ、本市の公共交通の支えになっています。
こうした効果について市長はどのように考えておられるのか伺います。また、このような効果こそ市民に示すべきではないのか、市長の認識を伺います。
2つ目は、新制度案への移行の考えについてです。
市長は、1月27日の記者会見で記者から「予算案が可決した場合、敬老パスの制度現行案は、2026年度に新制度に移行するという理解でよいか。あるいは、可決後、2026年4月までの間に再度見直す余地は残されているのか」と質問され、「可決いただけるとすれば、これを前提に実施していくものと考えております」と述べています。今回の予算に計上されているものは、「現行制度を実施するための敬老優待乗車証交付費及び、制度改正に伴うシステム改修費約68億円」「健康アプリのモニター事業費等3億4,000万円」ですが、これらの予算案が可決されることで2026年度4月から予定されている、市長提案の新制度、利用限度額を7万円から4万円へ引下げ、自己負担は50%に引き上げ、対象年齢を70歳から75歳へと引き上げるという変更案の実施が認められたことにはならないと考えますが、改めて、記者会見での市長答弁での市長のお考えについて、その主旨を伺います。また、そのお考えが市民理解に沿うものなのか伺います。
4点目は、中小企業の賃金引上げにつながる支援についてです。
1つ目は、国会の付帯決議に基づく支援についてです。
最新のデータである2021年度、本市の全事業所数は約7万1千、そのうち99.9%が中小・小規模企業です。従業者数は全事業所で約92万人となっています。
厚生労働省は、「賃金引上げによる経済等への効果」について、「賃金引上げによる家計所得の増加は、消費を通じて経済成長に繋がり、さらに雇用や生産、消費が生まれるという好循環をもたらす(可能性がある)」と報告しています。
本市でも、市内経済の底上げには、労働者の賃上げが欠かせないことは共通の認識であると思います。
予算では、市内経済発展の好循環をつくる具体的な施策が必要と考えます。
北海道の最低賃金は、前年比50円upの1,010円になっています。事業者が従業員の賃金を上げる場合、時給増に加え、雇用保険などの労働保険料や健康保険など社会保険料の負担も増え、最低賃金が1,500円になった場合、労働者一人につき年間100万円以上の負担が増えると試算されています。
小規模事業者からは、「従業員の賃金をあげたいけれど、事業者負担が重く、ほんとにつらい」という切実な声を聞いています。
国会において採択されている小規模企業振興基本法には、付帯決議として「法人事業所及び常時従業員5人以上の個人事業所に義務付けられる社会保険料が小規模企業の経営に負担となっている現状があることに鑑み、小規模企業の事業の持続発展を図るという観点に立ち、従業員の生活の安定も勘案しつつ、小規模企業の負担軽減のために、より効果的な支援策の実現を図ること」とされております。
この付帯決議の立場に立ち、効果的な小規模企業への支援策として、税や社会保険料の負担軽減措置を実施するよう国に求めていかれるのかお伺いします。
2つ目は、中小建設業の賃上げの取組についてです。
帝国データバンクによると、市内建設業の過去5年間の倒産件数は、2020年11件、2024年30件と5年間で約3倍と右肩上がり、全産業の倒産件数に占める割合も16%から26%に引きあがっています。
市内建設業は公共工事や除雪の担い手として、重要な役割を果たしていますが、高齢化が著しく後継者への技術継承による人手不足の解消が急がれます。業界の重層的な構造から、とりわけ中小事業者が多い下請けや孫請けの事業所で働く従事者の賃上げが実現できるよう行政の取り組みが大切と考えるところです。
昨年、国会でわが党も含めた賛成で成立した改正建設業法は、業界が、工事着工後の資材高騰のリスクや追加費用を負担する慣習が相まって、労働者の賃金や労働時間へのしわ寄せが続いていることから、いわゆるダンピング、廉売行為の取り締まりの際の基準として、適正な賃金の目安となる労務費の基準として、「標準労務費」の制度を新設しました。
「労務費の基準」の作成にかかわって、国は地方自治体の意見を聞くことができますが、義務とはされていません。
札幌市は、「標準労務費」制度を中小建設業に行き渡らせるため、どのような取り組みをすすめ、また国にたいして、法改正の実効性を高めることを要望していくことが必要と考えますがいかがか伺います。
5点目は、都心部の大型再開発事業についてです。
再開発補助金は「北5西1・西2地区」の開発の遅れによる減額のみで、北5西1・西2地区を含め、北4西3地区、大通西4南地区と、3カ所の民間再開発促進費として、前年度比約40億円増額の予算106億円が、ほぼ予算要求通り計上されています。大型再開発事業への補助金について市長は、第4回定例会代表質問で「固定資産税の税収増などが見込まれる将来を見据えた投資として必要なものである」との認識を示し「補助の妥当性を判断しながら必要な支援を行う」旨の答弁でありました。
現在、暮らしに困っている市民にとって、「どのような妥当性があるのか」「現在の暮らしへの投資でこそ将来の安定が保障されるのではないか」などの思いがあり、市民感覚とのズレは大きくなるばかりではないでしょうか。
都市再開発法では、「再開発事業費の一部を補助することができる」となっており、補助をするかしないか、補助の対象や補助金額は自治体の判断で決められることとなっています。
本市の再開発事業に対する補助率は、北5西1・西2地区で17.5%。北4西3地区で23.1%ですが、建材価格の高騰や人手不足により、総事業費が増えることに伴い、補助率が変わらなくても補助金が増額することになります。
補助金の増額という公費負担が膨らむことが分かった時点で、事業や補助の見直しの検討を行うべきでした。
大型再開発事業の恩恵は大企業に集中しており、市内中小企業・小規模事業者には、下請けなどでどれほど仕事が回っているのでしょうか。
再開発事業は、見直しを行う検討が必要と思いますがいかがか伺います。
次は、北海道新幹線札幌開業延期が及ぼす影響についてです。
質問の第1は、延期に伴う市民への説明についてです。
北海道新幹線が開通してから間もなく9年、毎年100億円近い営業赤字を出し続けています。
機構や市は、札幌延伸が実現すれば、乗客数や経済波及などで最大限の効果が発揮されると説明されてきましたが、新函館北斗-東京間の運賃は、約5年前が片道2万2,690円でしたが消費税増税もあり、現在は2万3,430円と上昇し、所要時間はやっと4時間をわずかに切ったところで、その短縮は容易ではありません。1万円を切る格安航空券が普及するなかで、札幌延伸が実現したからといって、航空路線より優位性のある交通機関として需要が見込めるのか見通せない状況です。
鉄道・運輸機構が実施した2023年の再評価では、「費用対効果」の算出が0.9に落ち込みました。費用に対して効果が低いと判断される1を割り込んでいます。
当初の総事業費約1兆6,700億円は、予期せぬ自然条件への対応や資材高騰などにより、約6,450億円増額され、本市が支払う建設負担金は、2014年から2023年の10年間で約133億1,200万円にのぼり、24年度は約50億円、25年度は約56億円が計上されていますが、札幌市は「負担する工事の範囲における工事費は示されていない」ことから「札幌市の負担は示すことはできない」と説明しています。
税金を投入して進められる巨大公共事業について、市の負担金がいくらになるのか示すことができないということでは、市民の納得は得られません。
国が札幌延伸時期の見通しをつける作業に入っていますが、2038年前後まで開業の時期がずれ込むといわれるなか、札幌市として、改めて立ち止まり、建設負担金の見通しや、新幹線札幌駅での利用者数など需要予測を明らかにし、市民への説明責任を果たすことが必要と考えますが、市の認識をうかがいます。
質問の第2は、トンネル発生土の市民生活への影響についてです。
市内工事で掘削される発生土約230万㎥のうち、約50%の約115万㎥がヒ素・鉛・カドミウムなど重金属を含む要対策土と言われ、粉じんによる健康リスクや地下水への影響がないように対策を実施すると説明していましたが、受入候補地とされた手稲区金山地区と厚別区山本地区や、現在の受入地である手稲区手稲山口地区の周辺住民からは、繰り返し反対署名が集められ市へも届けられてきました。
さらに、丁寧な説明をするとしながら、説明会の対象を狭め、事前調査に踏み切ったことや、調査結果の説明の場で発生土搬入の時期を示すなど、なし崩し的な機構や市のやり方に対し、住民からは怒りや不信が示されてきました。
本市は、2021年の総合交通調査特別委員会において、手稲山口地区のみでは全量の受入は困難とし、金山地区及び山本地区、またそのほかの受入地確保も含めて取り組んでいく旨の答弁をされていますが、市長は、大幅に工期が伸びることが確実となっているなかで、さらなる受入地の検討をすることが、住民の怒りや不安を呼び起こすことになるという考えを持たれないのか、要対策土を運び込むことはやめ、金山や山本地区の候補地を白紙に戻すお考えはないのか伺います。
次に、温室効果ガス削減についてです。
2016年に発効した、国連気候変動枠組条約締結国会議による「パリ協定」で、地球の平均気温上昇を産業革命以前との比較で2℃未満に抑え、1.5℃に抑える努力を、世界に向けて強く呼びかけました。
質問の第1は、国の「第7次エネルギー基本計画」についてです。
昨年12月、政府は「第7次エネルギー基本計画案」、「地球温暖化対策計画案」、「GX2040ビジョン」を策定、公表し、パブリックコメントを経て、2月18日に閣議決定されました。昨年、GX推進法を制定し、原発に回帰する方向へと舵を切りましたが、今回の「計画」は、「原子力発電の重要性は高く、その活用を進める。」「再稼働の加速」に向かうための理解促進に取り組むなど、2011年に起きた福島第一原子力発電所の事故を、真摯に反省しているとは到底思えないものとなっています。
原発を「脱炭素電源」として活用し、そのために、これまでの「40年から60年」としていた原発の運転期間について、「60年のカウントから除外する」ことを認め、「次世代革新炉の開発・設置」まで取り組もうとする、驚くべき計画です。
原発は、「トイレなきマンション」と言われるように、安全な処分方法が確立されていません。地震が多い日本の国土では「安全」な原発などありえず、フクシマで被災した住民は、未だ、ふるさとに帰ることができず、生活再建もままならない状況です。この深刻な事故から得る教訓は、「人類と原発は共存できない」ことであり、フクシマを繰り返さないためには、原発依存から脱却するしかありません。
計画に示した2040年度の電源構成は、原発を「2割程度」としていますが、そもそも安全な処理方法が確立されていない放射性廃棄物を生み出す原発を、電源構成とする計画など、あってはならないのではないでしょうか。さらにはLNG液化天然ガスや石炭などの火力発電を「3~4割程度」と、温室効果ガスを排出させる電源も温存したままであるうえに、2月8日、石破首相は、トランプ大統領との会談後、米国から日本へのLNG液化天然ガスの輸入を拡大する方針を発表しました。
これまでいみじくも原発を「低減」する目標にしていたことに比べ、あきらかに推進する立場を表明する計画だと思いますが、市長の評価をうかがいます。IPCC気候変動に関する政府間パネルの「1.5℃特別報告書」においては、1.5℃の上昇を抑えるため、2030年までに、世界の二酸化炭素排出量を2010年比で約45%削減する必要が指摘されていますが、化石燃料利用を温存する国の現行計画や、新たな「計画」は、国際的な削減目標を達成できるものとなり得るのか、市長の見解をお示しください。
質問の第2は、札幌市の温室効果ガス削減についてです。
本市は、2008年に「環境首都・札幌」宣言を行い、2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡が保たれる「ゼロカーボンシティ」を実現するため、「気候変動対策行動計画」を2021年3月に策定しました。その達成に向け、2030年までに、2016年比55%から60%の削減を行うための、具体的な行動計画が示されています。いよいよ、中間目標まであと5年という、一つの節目が近づいています。
本市は積雪寒冷地であることや、第3次産業中心の産業構造であること、日常生活における自動車への依存度が高いことなどを踏まえ、5つの施策を設定しました。「徹底した省エネルギー対策」の施策では、住宅のZEH化や省エネ暖房・給湯機器の導入などが進められ、住宅への太陽光パネル等の設置補助で、「再生可能エネルギーの導入拡大」の施策も行われています。
1点目は、移動の脱炭素化についてです。
5つの施策の3つ目に「移動の脱炭素化」を掲げ、EV、FCVなど環境負荷の少ない次世代自動車の導入を促進しようと、現状22%の自動車保有台数に占める割合を、2030年までに60%にし、公共交通利用の推進等とあわせ、132万トンCO2を削減する目標となっています。併せて、「公共交通の利便性向上と過度な自動車利用の抑制による人と環境を重視した都心交通環境の創出」を都心まちづくり計画に掲げています。
しかし、近年、本市でも地下鉄や市電、バスなどの乗車料金が値上げされ、路線バスの減便・廃止が相次ぎ、これまで以上に公共交通機関を利用しづらい市民が増えているのではないかと考えます。また、賃上げ等が物価上昇に追いつかない昨今で、安いとは言えない次世代自動車を購入できる市民は限られています。
次世代自動車の普及に頼ることなく、公共交通の利用促進を図ることが急がれると考えますが、いかがですか。市内の中心にある創成川通りに「都心アクセス道路」を建設しようとしていますが、都心部の目指す姿、「過度な自動車利用を抑制」できなくなると考えますが、いかがですか。公共交通の路線充実と、歩く距離ができるだけ短くなるシームレスな乗り換え環境の整備などで、公共交通利用による移動の脱炭素化を図ることを優先すべきだと考えますが、いかがですか。
「移動の脱炭素化」の施策における、現状の温室効果ガス排出の削減量は、いくらなのか、直近の数値をお示しください。また、都心部における自動車利用の抑制策をどのように考えているのか、あわせてお示しください。
2点目は、市有施設の温室効果ガス排出量削減の取組についてです。
各区役所や学校などの市有施設は、市域の温室効果ガス排出量の約6%で、本市は市内最大級の排出事業者となっています。そのため、「気候変動対策行動計画」では、市役所編を設け、2030年の温室効果ガス排出量を29.2万トンCO2まで削減することを目標にしました。
1998年度から児童会館、小中学校等市有施設への太陽光パネル等、再生可能エネルギーの導入が始められ、施設によって、小型風力や小水力発電なども設置されてきました。2022年度の市有施設等での速報値は、65.4万トンCO2排出量となっており、前年度より減少したものの、歩みが遅いのではないでしょうか。
その間に、再生可能エネルギー技術は進化しています。太陽光発電を例にとれば、導入時の1998年は、まだパネル自体に重量があり、1枚のパネル面積に対する発電量も現在の2分の1程度で、電気を貯めておく蓄電池との接続なども高価なものでした。研究開発が進み、ポータブルな太陽光パネルや蓄電機器などが店頭で売られるようになり、発電量・蓄電量は大きく、重量は軽く、柔らかくなり、市場に出回ることで価格も下がっています。また、建材一体型の太陽光発電ガラスなど、次世代型の研究・開発がさらに進められています。
これまでは屋根に設置して、定まった方向から太陽光を受けるタイプのパネルが主流でしたが、新たな技術により、パネルの角度や向きの自由度が高まり、壁面や窓などにも設置できるタイプも作られています。リチウムイオン蓄電池をセットで設置すれば、工夫次第で必要電力の多くを再生可能エネルギーで得ることができ、災害時等に持ち歩きができる軽量サイズも作られるようになっています。
市有施設には、まだ省エネルギー・再生可能エネルギーの設備が導入されていない施設があります。老朽化等、設置に課題を抱える施設でも、軽量で容量の大きい発電・蓄電のしくみを取り入れていくことは可能ではないでしょうか。また、学校などすでに設置した施設でも、10キロワットアワー程度では、必要な発電量には及ばないと考えます。設置済みの施設に対し、発電量をさらに増やすなど、日々急速に進化している再生可能エネルギー技術を取り入れながら、CO2排出量削減をいっそう進める工夫が必要だと考えますが、いかがかうかがいます。
3点目は、大倉山の樹木伐採の影響についてです。
このたび本市は、大倉山ジャンプ競技場等について、競技場改修費等に2億100万円を予算計上しました。この中には、ラージヒルの北側にノーマルヒルを併設するため、大倉山に植生している約1,000本の樹木を伐採する想定の「環境保全対策検討費」が含まれています。
ノーマルヒルのスタート地点となる周辺を、樹木の伐採などで整備する方向で、対象となるエリアの一部は、民間が所有する、本市が守るべき天然林です。1939年から、大倉山一帯は、みどりと環境を保全するために第一種風致地区に指定され、880ヘクタールもの森林に植生してきた樹木を守ってきました。このエリアにある樹木を、「維持管理費の低減」や「大会運営等の効率化」を理由に伐採していいのでしょうか。
東京都では、明治神宮の外苑を、野球場やラグビー場の整備を含む再開発で619本の樹木を伐採することに、スポーツ選手も含めた著名人がよびかけて反対の活動が広がっています。
このたび策定した本市の「森づくり基本方針」では、100年後の森林の姿は、「保全された天然林」はそのまま保全し、人工林は、天然林に移行する森林と、手入れした健全な人工林にすることを目指しています。天然林である大倉山の樹木の伐採など、あってはならないのではないでしょうか。また、本市の「気候変動対策行動計画」では、天然林は保全されていることを前提として、吸収量と排出量の均衡を保つゼロカーボンの実現を目指しています。
大倉山の樹木の伐採は、天然林はそのまま保存するという本市の方針に反し、吸収できるCO2を人為的に減らすことになると考えますが、いかがですか。
天然林は、その姿を形成するまでに100年単位での長い時間を要します。環境保全策として「移植や植樹」を行おうとすることは、気候変動対策行動計画が踏まえる「第2次環境基本計画」に掲げる「自然環境の保全と生物多様性」への配慮がなされないことになりますが、見解をあわせてうかがいます。
4点目は、現状の温室効果ガス総排出量抑制の進捗状況と促進についてです。
2022年度の速報値では、全体は少しずつ削減が進んでいるものの、55%から60%削減に対して14%、10%と、目標に程遠い状況です。本市は「2050 年を待つことなく2030 年度までに、カーボンニュートラルの実現を目指す」地域として「脱炭素先行地域」に選定されており、太陽光や地中熱など再生可能エネルギー設備整備のための「地域脱炭素推進交付金」も受けることができます。
我が党が、議会でたびたび取り上げている、集合住宅に対する高断熱化やその改修、まだ導入していない市有施設への省エネ・再エネ設備の導入、外断熱工法を取り入れた市営住宅改修など、やるべき課題は山積しています。
本市が財政出動を検討する際、費用対効果だけでなく、温室効果ガス削減に貢献することに重点を置いた評価を行い、諸施策について、予算枠や対象事業の拡大、設置する再生可能エネルギー量の大型化や追加など、促進を図ることが肝要だと考えますが、いかがかうかがいます。
また、2030年まであと5年の節目を迎えましたが、今後どのような点を見直して、2030年目標達成に向かわれるのか、うかがいます。
次に、訪問介護事業所への支援についてです。
質問の第1は、札幌市の介護報酬改定での影響と現在の状況についてです。
本市の高齢化率は加速しており、2030年には市民の約3割、2050年には約4割が65歳以上の高齢者になることが予想され、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が一般世帯に占める割合は、年々増加しています。身体が弱くなったなどの場合の生活場所については、高齢者の約6割が在宅生活の継続を希望しています。
本市の「地域福祉社会計画2024」では、「在宅生活を支援するサービスの充実」を掲げ、「必要な支援を受けながら住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、在宅福祉に関するサービスの充実を図ります」と書かれています。
訪問介護サービスの利用者数は2024年1万5760人、2025年1万6113人、15年後の2040年には2万3857人と見込んでいます。
「介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続ける」ことは、多くの市民の願いでもあります。そのためには、訪問介護事業所が欠かせません。訪問介護は、とりわけ個別性が高く、利用者とホームヘルパーとの心を通わせるつながりで支えられ、成り立つものです。
しかし、在宅介護の根幹を支える訪問介護サービス事業所はというと、昨年9月「介護に笑顔!北海道連絡会」による調査では、4月の介護報酬改定で基本報酬が引き下げられた結果、札幌市内の、ヘルパー5名以下の事業所では、約3割が閉鎖、休止を検討していると回答しています。
本市では、訪問介護サービスを利用したい人は増えるものの、サービスを提供する事業所は事業の継続が見込めない状況であり、市民にとっては、「介護保険料を払っているのに必要なサービスを受けられない」「在宅での生活が継続できない」となることが迫りつつあります。
今年1月の東京商工リサーチの報告では、2024年の介護事業所の倒産は172件で過去最多、そのうち訪問介護事業所が81件で半数近くを占め、職員10人未満が95.1%で大多数が小規模事業所だったということです。
我が党は第3回定例会代表質問で、「報酬引き下げによる市内の介護サービス提供事業者への影響を把握する必要」や、「倒産などに至る前に手を打つ必要がある」ことを質問、再質問で求めたところ、町田副市長は「日ごろからの事業者のみなさんとのやりとりのなかで、介護報酬改定に伴う影響について注視しながら今後の動向、必要な対応を検討してまいりたい」とのご答弁でありました。
その後、訪問介護事業所の介護報酬改定での影響や運営状況、また廃業の場合の理由などを把握されてきているのか伺います。また押さえている場合現在の状況をどう捉えているのか伺います。
質問の第2は、事業継続のための支援についてです。
3定代表質問の答弁で、さらに「新規事業者数が廃止事業者数を上回り、状況に大きな変化は見られず、地域の訪問介護サービス事業に顕著な影響は見られていない」と、いう認識を示されました。
しかし介護において重要なことは、「介護の三原則」の1つである、『生活の継続性』です。
介護サービス利用者にとって、慣れ親しんだ介護事業所の廃業や倒産は、高齢者の自立を支える基盤が失われ、在宅生活の継続が困難になります。
担当訪問介護員や事業所が変わらず安定していることが、利用者の健康や生活の維持にとって大事な要素となっているのです。
東京都世田谷区では 高齢者・障がい者施設への緊急安定経営事業者支援給付金で、介護報酬改定による倒産防止を重視し、年間介護給付費の不足分として、訪問介護1事業者あたり88万円の給付をしています。
また、訪問介護は車で郊外をまわることが多く、物価高騰による燃料費の負担が重いため、本市の事業者からも特に影響が大きいという声が出ています。
本市として、介護報酬改定による減収や物価高騰の影響を調査し、事業所の倒産を防ぎ事業継続ができるよう、訪問介護事業所等への支援を検討すべきと思いますがいかがか伺います。
最後に、教育の課題についてです。
質問の第1は、学ぶ環境の改善についてです。
2006年に教育基本法が、2007年に学校教育法が改正され、2017年からの学習指導要領改訂などで大きく教育改定がおこなわれました。
そして、経済、産業に役立つ「人材育成」という方針が取り入れられ、教育内容や単元、標準授業時間数を定められ授業を詰め込み、道徳の教科化、小学校での英語など授業数が増えても増員はなく、教員が長時間労働の常態化により疲弊する事態をつくり出しました。
そうしたなか、本市の教職員は自主的な授業研究や、子どもたちの変化に気を配り、困りごとを抱える子への対応、保護者や地域へ子どもたちの様子や成長を知らせる、そうした教師としての仕事に誇りを持ち、心をくだいています。現場の教員から「子どもと向き合う時間がほしい」という声が出されています。札幌市の教育がめざす人間像「自立した札幌人」のためには、教員が児童・生徒と関係性を育むことが大切であり、環境の改善は不可決です。
1点目は、教員の定数増についてです。
学習指導要領改訂により、1998年時6年生の標準授業コマ数が945時間から、2017年には1015時間と70時間も増え、ほぼ毎日6時間授業となりました。1年生でもほぼ毎日5時間授業です。
そのために、休み時間や給食時間短縮など、子どもたちの生活や学習を圧迫し、放課後児童クラブ指導員からは、子どもがぐったりしている、カリカリしているという声もきかれました。教員にとっても、放課後の業務時間が削られ授業準備の時間が不足し、持ち帰りや時間外勤務が増え、余裕がいっそう失われました。
本市の教員からも、子どもたちのことには時間や手間を惜しまないが、それ以外の業務に時間がかかり、一人の荷重が大きい、人を増やしてほしい、とお聞きしました。
本市では来年度に教職員88人が増員されますが、おもに6年生の35人学級化にともなうものです。
本市では、定数欠の他に病気療養、出産や育児休業などの代替が数カ月にわたり決まらないことなど、臨時教員でも埋まらない事態が起きています。また、非正規教員も担任を持つなど正規教員と同様の仕事をしているのが実情です。
本市の教員の勤務実態調査( H27)でも、休憩時間の自由利用について、「全く自由に利用できなかった」、「あまり利用できなかった」を合わせ87%であり、教員の時間がない様子が推察されます。
本市教員の働きかた改善のためには、正規教員を増やし、学校運営に余裕を持った教員配置が必要だと考えます。
教員の定数増が不可欠でありますが、いかがお考えか伺います。また、正規の教員で定数とすべきですが、いかがか伺います。
2点目は、中学校での35人学級についてです。
35人学級は、学習の理解が着実に深まる、教師の授業改善となる、など子どもと教師の相互関係を豊かにする経験が生まれています。また、昨年1定議会の代表質問で、「教員の定数増や少人数学級の拡大については、子ども1人ひとりに応じたきめ細かな指導など、教育活動を充実させる上で重要なものと認識」と教育長のご答弁がありました。
思春期となる中学生は、体が変化する成長期を迎え、大人と子どもの間で繊細に揺れ動く時期になるため、手厚い教育が引き続き必要です。
少人数学級は、教員は子ども一人ひとりの個性を理解し、子どもの変化を感じ取りながら向き合えます。できるだけ早い中学校での実施が望ましいと考えるものです。
国は、2026年度(R8)から3年かけて中学校で35人学級をすすめる方針を示しました。本市はすでに中学1年生を35人学級としていることから、26年度から1学年先行して、中学2年生からの35人学級を実施すべきと考えますがいかがか、伺います。
質問の第2は、教育の保障としての支援についてです。
1点目は、給食費無償化についてです。
学校給食費無償化は、2023年度に547自治体に広がりました。政令指定都市でも、福岡市では「これまでの学校給食の負担軽減にとどまらず」支援に踏み込む、と市長が無償化を表明、来年度から実施される予定です。京都市議会では、12月に小中学校の給食費無償化を求める決議を全会一致で可決しています。また、多子世帯の場合に給食費を減免、減額する手立てをとる自治体も広がっており、そうした一定の要件を定めている自治体を含めると全国で4割以上が無償化に取り組んでいます。
本市としても、給食費の物価上昇分の軽減にとどまらず、給食費無償化に踏み出すべきですがいかがか、伺います。
2点目は、教材費等の負担軽減についてです。
義務教育でも、給食費のほか、副教材やドリルなど授業に必要な教材費が学校で徴収されるほか、絵具や習字セット、リコーダーなども別途用意しています。本市の今年度の小学校6年生の例では、年間1万4千190円が学校諸費として徴収され、そのほか、修学旅行をはじめ校外学習等もあり、ある学校ではスキー授業のバス、リフト料金が1人7千円もの徴収だったとお聞きしました。
本市でも、中学入学時には制服、ジャージ代も値上がりして8万円以上もかかり、なんとかならないかという声が出ているところですが、教材費や制服等を補助する自治体は増えています。苫小牧市では今年度から中学制服代の半額程度、1万5千円を補助しています。品川区では教材費に続き制服の無償化を決めました。
本市としても、教育の保障として、保護者負担となっている学校で指定され購入するもの、また必要な教材費等の補助をおこなうべきですが、いかがお考えか、伺います。
3点目は、就学援助制度の拡充についてです。
わが党が2023年の第2回定例会で給食費などの軽減を求め質問をしたところ、「就学援助制度等」で支援をおこなってきたという答弁でありました。わが党は繰り返し就学援助制度の費目や対象の拡充を求めてきましたが、現在、就学援助を受けられる世帯の物価高騰の影響はより大きいことが推察されます。
入学費用、日常的にかかる教材費も上昇していることから、就学援助の支給金額を、物価上昇にあわせ当然ひき上げるべきですが、どう対応されるのか伺います。
さらに、物価高騰と最低賃金引上げなどを考慮し、対象となる世帯の所得基準を引き上げることについて、お考えを伺います。
以上で、私の質問のすべてを終わります。ご清聴、ありがとうございました。
秋元市長 答弁
全体で大きく5項目にわたりご質問をいただきました。私からは大きな1項目目、私の政治姿勢についての6点お答えをさせていただきます。その余のご質問に対しましては、担当の町田副市長、石川副市長、天野副市長、教育長からお答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
大きな1項目目は私の政治姿勢についてお答えをいたします。まず1項目目の石破政権と新年度予算案についてお答えをさせていただきます。政府の令和7年度予算案につきましては、経済や物価動向等に配慮しつつ、重要政策に重点化し計上したものと認識をしております。具体的には、こども未来戦略に基づく子ども子育て支援の本格実施や、投資立国の実現に向けたGX投資推進、AI半導体産業基盤強化といった重要政策課題に対応したものと理解をしており、今後、国政の場において審議をされていくものと認識をしております。
続いて政治姿勢についての2項目目の2025年、令和7年度予算案について5点ご質問がございましたので順次お答えをさせていただきます。まず1点目の重点支援地方交付金の活用についてであります。推奨事業メニュー分として示された財源の活用につきましては、学校給食の保護者負担を据え置くための公費負担や、市民への幅広い支援としての家事用水道料金の減額などに優先して取り組むこととしたものであります。また、住民税非課税か非課税世帯への給付金につきましては、2月中に給付を開始する予定でありまして、この給付金は、灯油価格の高止まりによる影響を受けている方々への支援にも資するものと認識をしております。加えて、積雪寒冷地であります札幌市におきましては、冬季のエネルギー需要、これが大きいことから、引き続き国に対し、エネルギー価格の負担軽減支援策の実施について要請をしてまいりたいとこのように考えております。
次に2点目の子ども医療費助成の所得制限撤廃についてであります。本制度の更なる拡充につきましては、子育て支援の面でも重要な課題と認識をしておりますが、将来にわたり多額の財源が必要となってまいりますことから財政状況を見極めつつ、今後も検討を続けてまいりたいとこのように考えております。
次に3点目の、敬老優待乗車証交付費の予算についてお答えをさせていただきます。敬老パスは、老後の生活の充実を図ることを目的とした制度として外出を支援してきたものと認識をしております一方、過去の制度変更で利用者負担と上限額を導入した際に、公共交通機関の利用状況に特段の影響変化は見られず、交通事業者の経営支援に寄与しているとまでは言えないと考えております。新制度案への移行につきまして、約1年半の間、市民や議会の皆さんと重ねてきた議論の経過でありますとか、パブリックコメント検討の結果を踏まえますと、現行制度を維持、敬老パスを廃止といった様々な意見がある中、今回の実施案については、様々な世代の方から一定の理解が得られる内容のものと判断をしたところであります。このため、今回の予算案につきましては、実施案の通り進めるものとして提案をさせていただいており、成立すれば実現するためのシステム改修に着手することとしております。
次に4点目の中小企業の賃金に賃金引き上げに繋がる支援についてお答えをいたします。
小規模企業への税や社会保険料の負担軽減に係る支援策につきましては、国において責任を持って実施すべきものと認識をしております。札幌市におきましては、原材料価格等のコスト上昇分が適切に価格転嫁され、市内の中小企業の賃上げに繋がるよう、引き続き国へ要望してまいりたいと、このように考えております。また、建設業における労務費の基準につきましては、本年の11月頃をめどに国が策定を進めておりますことから、その動向を注視してまいります。なお、制度の詳細が示されれば、企業や業界団体に対し、遅滞なく周知、その啓発に努めてまいりたいと考えております。
次に5点目の、都心部の大型再開発事業についてであります。市街地再開発事業は、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることにより、投資の魅力と活力を高め、まちづくりの課題解決に繋がることに加え、固定資産税の税収増などが見込まれる将来を見据えた投資として必要なものと認識をしております。現在事業中の事業は将来のまちの顔となる重要なものでありますことから、着実に実施されるよう、国の補助制度を活用し、国の要綱において補助対象と定められている項目について補助金により支援しているところであります。また、事業主体であります各再開発組合は、その施行に当たって、市内に主たる事業所等がある企業を活用する意向を示しており、経済波及効果も見込まれているところであります。経済情勢の変化等により、事業計画の見直しが必要となった際には、関係者としっかりと協議をした上で、補助の妥当性を判断しながら必要な支援を行い、引き続き世界を引きつける魅力と活力あふれるまちを目指して、市街地再開発事業を進めてまいりたいと、このように考えております。私からは以上です。
町田副市長 答弁
私からは大きな4項目目の訪問介護事業所への姿勢についての2点の質問についてお答え申し上げます。1点目の札幌市の介護報酬改定での影響と現在の状況についてお答え申し上げます。訪問介護事業所から提出される廃止届のうち、事業所統合によるものを除きますと、主に人材不足や利用者の確保の困難さ、そして事業収益の減収が要因として挙げられているところでございます。現在訪問介護事業所の現状につきましては、北海道と北海道ホームヘルプサービス協議会が連名で実態調査を行っており、札幌市も協力して対応しているところでございます。この調査結果も含めて今後の状況を注視してまいりたいと考えるところでございます。
次に2点目、事業継続のための支援についてでございますが、報酬改定後の訪問介護事業所の経営支援に関しましては、国は令和6年度の補正予算におきまして、サービス提供体制を支援する事業等を実施することとしているところでございます。札幌市におきましても、関連した補正予算を提案しているところでございまして、新人ヘルパーの定着を促進する事業等を通して経営を支援していきたいと考えるところでございます。今後も介護事業所を取り巻く状況を注視しつつ、国や道と適切に連携し支援してまいりたいと考えるところでございます。私からは以上でございます。
石川副市長 答弁
私からは大きな3項目目、温室効果ガス削減についてお答えを申し上げます。まず1点目、国の第7次エネルギー基本計画についてであります。国の第7次基本エネルギー基本計画につきましては、同時に議論されてまいりました地球温暖化対策計画で示されておりますパリ協定および1.5℃目標と整合した2040年の温室効果ガス削減目標の達成に向けた、国のエネルギー政策の考え方が示されたものと認識をいたしております。エネルギー政策は市民生活や経済活動の基盤となるものでありますことから、再生可能エネルギーや原子力発電に関する基本的な考え方と具体的な進め方などにつきましては、国が丁寧に説明する必要があるものと考えております。
次に2点目、札幌市の温室効果ガス削減についてであります。まず最初に、移動の脱炭素化についてであります。次世代自動車の普及に頼ることなく、公共交通利用による移動の脱炭素化を優先すべきとのご指摘についてでありますけれども、日常生活における自動車の依存度が高い札幌市では、環境負荷の少ない次世代自動車の普及と公共交通の利用促進を両輪として取り組むことが必要であると考えているところでございます。公共交通の利用促進につきましては、面的なネットワークを維持するためのバス運転手確保に向けた取り組みや、交通結節点におけますエレベーターの設置など、乗りかえ環境の改善を進めているところであります。また、都心部への過度な自動車流入の抑制につきましては、例えば五輪通の拡幅など、骨格道路網の機能強化により、交通の分散化も進めるとともに、都心アクセス道路の整備により、創成川通の地上部や周辺道路から地下トンネルに交通の転換を図ってまいりたいと考えております。なお、移動の脱炭素化における温室効果ガス排出の削減量は、2022年度の速報値で約28万トンとなっております。
続きまして市有施設の温室効果ガス排出量削減の取り組みについてであります。市有施設における太陽光発電設備の導入につきましては、設置スペースの確保や建物の耐荷重などの課題に対応しながら進めていく必要がございます。そこで、まずは未設置の施設に軽量型の太陽光パネルの設置を進めますとともに、設置済みの施設につきましても、発電量を増やしていけるように、新たな技術の開発動向に合わせて、次世代型太陽電池の実証実験などを通じて、検討してまいります。
次に大倉山の樹木伐採の影響についてであります。大倉山へのノーマルヒル併設に当たりましては、環境への影響を極力抑えるため、1972年大会前まで雪印シャンツェが設置されておりました場所に配置することを想定しているとこところでございます。加えまして、敷地内での植樹等の保全対策を検討しまして、樹木伐採に伴うCO2吸収等への影響につきましても最小限にとどめていく考えであります。保全対策の検討に当たりましては、現在進めております環境調査の結果を踏まえまして、自然環境の保全と生物多様性の観点を含めて、今後、専門家等意見を伺いながら丁寧に進めてまいります。
次に現状の温室効果ガス総排出量抑制の進捗状況と促進についてであります。2030年目標達成に向けましては、今後も取り組みの強化が必要であると認識しており、より一層の徹底した省エネルギー対策と、再生可能エネルギーの導入拡大が不可欠であると考えております。そのため、地域脱炭素推進交付金や脱炭素化推進事業債など、国の財政支援を活用しながら、脱炭素先行地域で計画している取り組みも加速させてまいります。私からは以上であります。
天野副市長 答弁
私からは大きな2項目目、北海道新幹線札幌開業延期が及ぼす影響についてお答えをいたします。まず1点目の延期に伴う市民への説明についてですが、札幌市が負担する工事の範囲における工事費や新たな開業目標が示されていないことから現段階においては、建設負担金の今後の見通し等をお示しすることは困難でございます。そのため札幌市としましては今後も情報収集に努めるとともに引き続き国や鉄道・運輸機構に対しまして、1日も早い完成・開業やできる限りの地方負担の軽減を求めてまいりたいと考えております。また市民の皆様への情報提供につきましては、工事に関する説明会や出前講座、ホームページなどを通じて行ってきたところであり、今後も継続して取り組んでまいります。
次に2点目のトンネル発生度の市民生活への影響についてお答えをいたします。北海道新幹線の建設工事には、発生度の受け入れ地の確保が必要不可欠であり、手稲山口受入地のみでは札幌市内から発生する対策土全量の受け入れは困難と想定されます。そのため鉄道・運輸機構におきましては現在受入候補地である金山地区および山本地区の他新たな候補地の可能性を含め、受入地の検討を進めており、その決定にあたりましては住民説明会や事前調査、対策方法の検討を進めて判断していくものと認識をしております。いずれの場所、受入地に決定する場合であっても鉄道・運輸機構において、事前調査を行った上でしっかりと検討を重ね、周辺環境に影響を及ぼさない対策を行うことが重要であると考えております。
札幌市といたしましては鉄道・運輸機構と連携し市民の皆様の理解が深まるよう、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
山根教育長 答弁
私からは大きな5項目目、教育の課題についてお答えいたします。まず学ぶ環境の改善についての1点目、教員の定数増についてであります。教員の定数増につきましては、学校の指導・運営体制の充実に繋がり、全ての子どもたちへのよりよい教育の実現に寄与するものと認識しております。
働き方改革の推進につきましては、これまでも職員の意識改革、業務の見直し、外部人材の活用などの観点から、様々な取り組みを実施してきたところであります。札幌市としましては、引き続き国に対して、教職員定数の改善を要望するとともに、学校の働き方改革を着実に進めてまいります。また、教員の配置につきまして、正規教員の採用数は、将来的な児童生徒数の減少など、中長期的な視点で決定していることに加えまして、必要な教員数は翌年度の4月の児童生徒数により確定するため、一定数の臨時教員は必要であると考えております。
2点目の中学校での35人学級についてであります。札幌市で実施している中学校1年生の35人学級は、国の加配定数を活用しております。令和8年度からの中学校35人学級の実施につきましては、昨年末に財務大臣と文部科学大臣の間で合意されたところでありますが、今後、加配定数を含めた国の具体的な検討状況を見極めてまいりたいと考えております。
次に教育の保障としての支援についてであります。まず1点目の給食費無償化についてでありますが、学校給食費は令和2年度から保護者負担額を据え置いており、物価上昇が継続する中、令和7年度は公費負担を14億5000万円に拡大する補正予算案として、今議会に上程させていただいたところであります。給食費無償化につきましては、国政の場でも様々な議論が行われているところであり、引き続き、国の動きや物価の動向などを注視し、対応を検討してまいりたいと考えております。
2点目の教材費等の負担軽減についてであります。補助教材や旅行的行事等の費用につきましては、保護者負担を軽減する観点から、必要最小限の経費で、教育のねらいを達成するために、各学校に内容の精選や費用の削減を図るよう促してきたところであります。また、経済状況により負担が困難な家庭に対しては、就学援助制度に基づく必要な支援を行っているところであります。今後も引き続き、費用負担の軽減を図る取り組み事例について、各学校に周知するなど、保護者負担の軽減を積極的に進めるよう促してまいります。
3点目の就学援助制度の拡充についてであります。就学援助の支給金額につきましては、国が定める要保護児童生徒援助費補助金の改定に応じて増額してきたところであります。支給金額の見直しにつきましては、今後も国の動向を注視し、適宜対応してまいります。また、所得基準につきましては、社会情勢等に応じたものであるべきと認識しております。今後も必要に応じて検討を行ってまいります。私からは以上です。
佐藤議員 再質問
再質問について、敬老パスについてと、学校の教育の保障、2点について再質問いたします。敬老パスについてですけれども、市長はご答弁で、これまで1年半にわたって市民と、また議会で議論してきたと変更案について、パブコメで全世帯から一定の理解をいただいたと、この変更案でいくのだという旨お話されました。しかし、このパブコメでは、「現行の敬老パスを維持してほしい」というのが46%で、およそ半数であり、敬老パス制度の変更となる「実施案に賛同」は全体の31%でした。しかも、この数や割合について、1月27日の市長の記者会見では発表されていません。市長は、「現行敬老パスを維持してほしい」意見の46%については言及せず、31%、3割の賛同だけを切り取り、全世代から賛同いただいたと話されたわけです。また、2月14日の厚生委員会で記者会見時の523件と発表された意見の総数が457件と訂正され、そしてパブリックコメントに寄せられた意見についてもまとめられないまま、厚生委員会に間に合わなかったというのが実情です。
市長はパブコメの報告を受け、記者会見での発表をされたと思いますが、そのような不十分なままの報告を受けられ、現在の変更案が出されるまでに寄せられた5163件の市民からの意見のうち、「現行敬老パスを維持してほしい」という多数の市民からの意見と、このパブコメの意見から、賛同を得た、しかも、パブコメ直後、まとめられないうちに変更案でいくと決定していたという、あまりにも乱暴ではないかというふうに思います。
このパブコメが1月20日まででしたが、1月24日に新聞報道で、”敬老パス「上限4万円案」維持 札幌市方針”と出ました。1月27日の市長の記者会見で市長はこの報道内容と同様に話されましたので、既に内部で1月23日までに決定していたのではないかというふうにも推察いたします。市長へのパブコメの報告では、「変更案に賛同」31%と、「現在の敬老パスを維持してほしい」46%という、それぞれの数自体の報告があったのか、あるいはその数を知っていて、勘案せず判断されたのか伺います。
2点目に、学校の教育の保障としての支援についてですが、教材費について、必要最小限の経費にするよう、各学校への内容、費用の削減を図るように促していくと、そういうことですけれども、学校でするにはもう無理があります。既に学校では最小限にするように検討してきたと思いますが、副教材や副読本、これは変えようもありませんし、物価高騰で様々なものが値上がりしています。バス代も上がり、それを学校で何とかできるものではありません。もしもバス代が高いからと、その学習をなくしてしまうというようなことがあってはならないというふうに思うんですね。教育委員会として軽減していくことを検討すべきですが、いかがか伺います。
秋元市長 答弁
敬老優待乗車証に関してのご質問、まずお答えをさせていただきます。パブコメとの、それから最終的な判断との関係のご質問をいただきました。1月の20日にパブコメを終了いたしまして、これ速報値で今回いろんなご意見と、それから意見を自由記載していただくものがありました。これらについてできるだけ早く全体像を把握するためにですね、AI、人工知能を使った分析、こういった新しい技術などを使って速報値としてまとめたもので記者会見をさせていただきました。総数に違いがあったのではないかというご質問の中にもございましたけれども、この変動した理由は、同一の方から複数回にわたって同じご意見、反対意見が寄せられていた、こういったものは除いて修正をさせていただいた、そういう部分がございます。そういう意味では、記者会見の数字と、委員会報告させていただいた状況、精査をした状況と違っているというものがありますのでこれはご理解をいただきたいというふうに思います。
できるだけこういったご意見をいただく中で、私今回、このパブコメのご意見の大きく分類しますと、3つの分類になってます。1つは現行制度を何らかの形で、金額だとかも含めて何らかの形で、現行制度を維持してほしい、維持すべきだというご意見、それから一方で、もうむしろ制度はもう廃止してしまった方がいいのでではないかというご意見と、この修正案のように、一定程度の見直しをした上で残すべきと、こういう3つの分類になっておりました。そういった中で、もちろんこのパブコメは、賛否を、数を問うものでありませんので、全体の数字ではありませんけれども、私が一番今回重要視をした判断のところは、やはりこの世代間の対立、こういったものが継続しないようにしていかなければいけないということを重要視いたしました。制度を残してほしいというご意見の7割、8割以上の方は70歳以上の利用されている方でした。こういった方々のご意見ってのは、そうわかります。一方で制度そのものを廃止すべきというご意見、これは70歳未満の方が8割を占める、圧倒的に偏った世代に、ご意見になっておりました。それと比較をした場合に、この修正案については70歳以上の利用されてる方と、それから70歳未満の方との意見がほぼ拮抗していた。50%を超える方がむしろ70歳以上の方であった、こういったことから、いろいろな方々の世代の方々が納得できる案は、この修正案だということで、ほぼ拮抗した世代のご意見をいただいたということで判断をさせていただいた、このことを記者会見で申し上げたところであります。
山根教育長 答弁
私からは再質問のございました教材費等の負担軽減についてお答えいたします。先ほどもご答弁申し上げましたが、経済状況により負担が困難なご家庭に対しましては、学用品費や修学旅行費などについて、就学援助制度に基づく必要な支援を行っているところであります。また、義務教育における教材につきましては、現在、各家庭にご購入いただいている既存の教材の代替となるデジタル教材の整備を拡充し、各学校での活用を進めているところであります。
教育委員会といたしましては、このような取り組みを積極的に進めながら、学校とともに、保護者負担の軽減に引き続き努めてまいります。以上でございます。
佐藤議員 再々質問
敬老パスについて再々質問します。今市長からご説明ありましたけれども、今回パブリックコメントのことをお話されてましたけれどもね、議論してきたと。現在の変更案は策定の前に寄せられた5163件の意見のうち、無作為抽出で18歳以上の市民に送付され、答えていただいた敬老パスのアンケート、これが一番むらなく市民意見を寄せていただいたと思いますけれども、現役世代の負担だとか、高齢者優遇だという意見は、私これ1件1件数えましたけれども、0.3%しかありませんでした。ごくわずか、寄せられた意見をことさらに強調し、現役世代の負担だと言い始めたのは、市の方からであって、市民から声高に言ってきたわけではありません。そして世代間分断となってきました。また先ほど答弁の中で、公共交通への影響はないという旨の答弁もありましたけれども、交通への影響がないとすれば、生活への影響が大きいのではないかと、そういうふうに私は思いをはせるものです。そして、市の財政が大変ならばと、多少の負担はやむを得ないとまで言ってくれている市民に対し、あまりにも今回の決定は、あまりにも早く検討したのかどうかさえも疑わしい、不誠実ではないかというふうに思うんですね。真摯に向き合うべきではないんでしょうか。
そして、今年度予算の可決がされるとしても、市民の理解を得られたとは到底考えられません。市議会各会派においても予算に賛成すると、敬老パスの大幅な削減案を認めたと、市民は考えることになるんじゃないんでしょうか。敬老パス変更案について再検討すべきですが、お考えにならないか、再度お伺いいたします。
秋元市長 答弁
これまで様々なご議論をさせていただきました。先ほど申し上げましたように、市民の皆さんから今回パブコメについても、若い世代の方からも多く意見をいただいた、非常にいろいろな、自分事として関心を持っていただいたことだというふうに思います。
その内容というものは、しっかりと声を受けとめていかなければいけない。真摯に議論をしてきたからこそ、いろいろなご負担をいただく市民にご負担をおかけをするということは、これは首長として心苦しいことです。しかしながら、様々な財政運営をしっかりとやっていくために、責任を持った回答をしていく、その一つの判断をさせていただいたということであります。そういう意味ではこれまでの議論を踏まえた結論で、今回提案をさせていただきました。